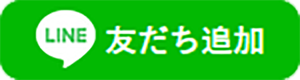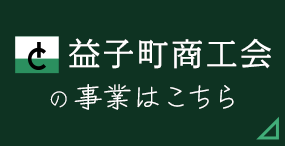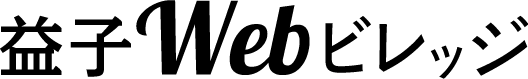 益子で生きる、益子を活かす
益子で生きる、益子を活かす
お店とヒトの魅力発見サイト

2024.01.24一部屋2000個の湯飲み

本日は、益子焼を製造されている、益子焼伝統工芸士の大塚一弘さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
大塚:お願いします。
まず初めに「清窯」という窯元の歴についてお聞きしたいと思います。
大塚:清窯は、父が昭和43年頃に独立開業しました。
私は二十歳の時から2代目として従事しています。清窯という屋号の由来は父の名前“清章(きよあき)”からとりました。
その当時、益子焼は作ればなんでも売れる時代でした。
成長期ですね。
大塚:そうそう、成長期だね。バブルが崩壊するまでは、まあそんなに悪くはなかった。
昭和の後期、一番盛り上がった、一番成長していた時期ですね。
大塚:とにかく作ればなんでも売れた時代で、大量に注文が来て仕事が切れなかった。その当時は登り窯(自然の傾斜を利用した益子では伝統的な焼成方法)しか無くて、年間3~4回くらい焼成していた。登り窯って相当な量が入る。うちの窯は6部屋あって大体湯飲みで計算すると一部屋に大体2000個ぐらい入った。
えー、すごい量ですね!
清窯の登り窯は、他の事業所さんのものよりも、すごく大きいイメージがありますね。





大塚:
現存している窯の中では大きいかもしれないけど、当時はそれでも中くらいだったかもしれない。大きい窯は10部屋とかあった。
登り窯って燃料をそんなにかけずに大量に焼けるから効率の良い窯なのよ。
信楽焼とか他の地域は、炎で土に自然の灰をかけていって仕上げていく、1週間とか2週間とか延々と焼いて、焼き抜くっていう焼き方なのだけど、
益子焼の場合はどちらかというと、たっぷりとした釉薬をかけて温度を加えて溶かすという焼き方なので、この登り窯っていうのは、益子焼に適した窯。
益子は燃料に使う赤松もあったし、
良い陶土も出たから、登り窯で大量に焼いて納めることができた。その当時は、本当に売れた。益子焼業界がどんどん成長していった時期で、その頃から独立していく方が増えてきたかな。
お父様もその一人だったと言うことですね。
大塚:そうですね。当時、(株)つかもと(益子町で最も歴史ある窯元の一つ)では研究生制度っていうのがあって、日中は会社の仕事をして夜は開放されて技術を学んだ。私の父が加守田章二さんと二人で釉薬の勉強してきたのが最初。今の窯業技術支援センターの前身だね。その後私の父が(株)つかもとから独立してこの場所に窯を築いた。
そうですか。良い制度があったのですね。
大塚:父は絵付けが得意だったので、絵皿がもうほぼ主流の仕事だった。
当時は冠婚葬祭とかいろんな部分で使ってもらった。30センチの皿が
毎月100枚、40センチの皿が毎月50枚出荷される。それがずっと続いている状態。
なるほど。すごい時代でしたね。
大塚:父の仕事を手伝いながら一日中絵付け。うちの絵付けの仕方って、筆とスポイトで書いていく特殊な書き方なのよ。コバルトっていう青く発色する釉薬を使って大胆な絵を描いたっていうのが、他の窯元とは違うところかな。
1枚1枚、当然、手作りですよね。
大塚:そう。私が帰ってきてからは、父は一日にせいぜい書いても50枚位だったかな。結構手間がかかる書き方なのでまず下書きを軽くして、スポイトで縁取りをして、中を染めて、筆で枝とか書いて、最後に釉薬を掛ける。
一日50枚ってすごい数に聞こえますが。
大塚:まあ、同じ絵を描いていたからね、パターン化されているから。
父は縁取りだけして、仕上げをするのが私の役目。
共同作業だったのですね。
大塚:そう。その当時最多に書いたのは一日100枚かな。100枚書いて薬掛けして仕上げた。



教わったのはたった一回
先代から色々学んできたと思いますが、どのように学んできたのですか。
大塚:大体後継者は指導所に入って基礎を勉強してから戻る。
指導所(現・窯業技術支援センター)は 最初の1年は伝習生としてろくろの勉強で、2年目は研究生として釉薬の勉強するところでした。
でも私の場合は違った。指導所に「来なくていいんじゃない。」「お父さんに教わった方がいいんじゃない。」って言われた。その当時の職員さんたちは、みんな父の後輩で教えづらかったみたい。
え~、そんなことあるんですか。
大塚:でもろくろの勉強がしたくて、どうしても指導所に入りたかった。結局、本来2年目から勉強する研究生の方に入ったらどうかって言われて最初から釉薬の勉強をした。
だから、ろくろの先生は父。最初に父から出された課題は、一日に100個湯飲みが引けるようにすることだった。
毎日100個ですか。気が遠くなる作業ですね。
大塚:最初は100個できないよ。なるべく多く作って、それをまた土練機にかけて潰して粘土に変えて、何回も何回も捏ねて。1年ぐらいしたら、今度はその中で形のいいものだけとっておけって。次はそれを削る作業。この削る作業も勉強もしないとできない。でも、どうしてもたくさん作れないのよ。
実は
指導所に入る前に専門学校に行っていて、磁器の専攻だった。陶器じゃなくて磁器だった。だから引き方も全然違う。それで父からは「それは益子の引き方じゃないからたくさん作れないぞ、じゃあ1回だけ教える」って言われて、教わったのはそのたった1回だけ。
お父様から、たった一回だけ?
大塚:そう、父が真ん中に座って、私が端に座って。で1回だけって言われて。横から見て益子引きを教わった。あとは隣にいて父がやっているその仕事を横で見ながら 目で見て覚えてく。
手取り足取りじゃなく、見て盗む。職人あるあるですね。
大塚:そう。失敗を積み重ねながら学んでいった。
だから誰にもほとんど教わってない。ただただ見ただけ。 結局、技術のある職人さんのところに行って、見て覚える。私は伝統工芸士ではあるけど、先生はいない。
独自で技術を盗んで、覚えてきたことを もう1回やるわけ。でも、どうしてもできない。そういう時はまたその先輩のとこ行くのだけど、先輩教えてくれないから。
どこに行っても見て覚えるのですね。
大塚:そう、でもそれが1番早い。理屈じゃないからね、技術って。
1番早いですか。
大塚:1番早い。目で覚えるのが1番早い。
専門学校に行っていた時に、粘土を練る試験(菊練り)があって、1回もやったことないのにできちゃうんだ。見て覚えているから、スタートから全然違う事を実感していた。
とにかく目で見ればなんとかなると思って先輩のうちに行くのだけど、教えてくれない。だから、私が行くとすぐろくろから降りちゃうわけ。同業者として見られたくないのかもしれない。清窯の息子だって知っているからね。だからいつもお茶の時間(10時とか3時)少し前に「自分はお茶飲みに来ましたよ」っていう感覚で行くことにした。そうすると、ろくろから降りない。作業の追い込みしているから。
なるほど。考えましたね。
大塚:先輩たちも、私が技術を盗みに来たって分からないから。これは良いぞ、と毎日行った。
ある種の気遣いみたいな感じも含まれていますね。
大塚:はじめは大物を作る人のところに行って、次は小物。
榎田さんのという方がいて、すごく手が器用で指先が長い。すごく細かい仕事もできる方。そこにもお茶飲みに行くのだけど、榎田さんは最初から私が技術を見たくて来ているってわかっていた。2日目に行った時に、「お前、
引き方教えてほしいんだろ。1回だけ見せてやる」って言われた。
やはり1回だけ。
大塚:1回。でも、その1回で自分がずっと疑問に思っていたことがわかった。先輩は俺と指の長さが全然違う。だから、あの引き方ができるんだと思った。俺は指が短いからできない。その時先輩が、「短ければ道具使えばいいじゃん。別に、『これ使ったからダメだ』と言うのはないんだから。出来上がりが同じくなればいいじゃん。」って。そこで「別に技術って自分なりにアレンジしてもいいんだな」と知った。
なるほど、深い話ですね。
大塚:益子では「菊練り3年、ろくろ6年、自走り1年」と言って10年で1人前と言われる。
そのようにして学んできて、自分なりの作風っていうのを作ってきたのですね。
大塚:当時は、自分の作品を作れなかった。「俺の作品だよ」って言えるようになったのは、ここ20年ぐらいかな。時間かかるし、誰が見ても自分の作品だって分かる作品作りって結構難しいと思う。






焦っている時は上手くいかない
今メインにやっている事は何ですか。
大塚:今は自分の作品よりもお客様からの受注が多い。普通、作家さんは受注はやらない。自分の作りたいものを作って、それを個展とかで発表して買ってもらう。だからお客様から、“こういう形、こういう色にできないですかね”って相談に来られると面倒くさくて嫌になってしまう。作家って「何であなたの希望で私が作んなきゃならないんだ」っていう気構え、ハングリー精神があるから何とかして自分の作品を作って、世に出して売るんだっていうところがある。
私も、いろいろな先輩方と出会って、作家の仕事をしたい、作家になりたいって思っていた。製陶業(作家)の方が心地いいんだよ。自分の作ったものを発表する場があるから。「大塚一弘」を売り出したい、
誰が見ても「これ大塚一弘さんの作品ですね」って言ってもらえる仕事ね。
なるほど。作家としては自分の作品を広めたいですものね。
大塚:でも実は、今は作家をしながら半分は受注の仕事もやっている。
変化してきたのは今から
12、3年前からかな。その頃から少しずつ益子焼が下降していた。仕事が少なくなってきて。
はい、注文が来なくなった。
大塚:別に父の力が無くなったとかではなく、益子焼全体がそういう感じになってきた。バブル崩壊して5年後くらいから徐々に注文が目減りしていった。100単位のものが 数十個単位になって、最終的に数個単位になってくる。お店側が在庫を持っていた時代から、窯元が在庫を持つようになった。電話1本で「これと同じ商品はないですか。」「これと同じような形ないですか。」って。その頃からこのままでいいのかなって疑問を持ち始めたんだよね。
バブルが崩壊して日本経済が不景気になりましたもんね。
大塚:自分の作品も作らないといけないし、焦っていた。これまで大塚清章(父)が作ったものを真似て作っていた。清窯ブランドを作っていたけど売れなくなってきて、だから早く自分の作品作らないとって。その頃は結構個展とかもやったのだけど、焦っている時ってうまくいかないのよ。
分かる気がします。焦っている時ってうまくいきませんよね。
大塚:どういうもの作っていいかわからないから、今までやったことのない分野のところに行ってみたりして。
現代アート、現代美術をやっている先生のところ行った時に「
別にそんな堅苦しく、こっちかな、こっちがダメならこっちに行こうとか考えすぎなくていいじゃん」って言われた。
自分の中では作家の仕事と他の仕事は違うって分けていた。でもその一言で、「あ、そっか、意識しすぎていたんだ。もっと自由にやった方がいいな。」って考えて。作りたいものを作ればいいんだっていう。
なるほど、それが転機になったのですね。
大塚:そう。

作っていくのも伝統
大塚:同時期に、starnet(益子町でコーヒーショップ、食材、食器、服飾等の販売をしているお店)の馬場浩史さん(元事業主、土祭をプロデュース)に売れなくて困っているという相談をしに行ったら、馬場さんに一言、「じゃあ、僕と仕事するかい。」って言われた。
最初に相談したのが、2010年の夏の頃だったのかな。自分の今やっている仕事を整理しながら、いつ頃から始めようかって段取りして、年明けにこういうもの作りましょう、ああいうもの作りましょうって感じでサンプル作りをずっとしていた。そんな時に「大塚さん、毎月どのぐらい稼げればいい」っていう話になって、生活費がこのぐらいだからこのぐらい欲しいですねって言ったら、「僕はそれを全部保証するから。サンプル作りからちゃんと市場に出して売れるようになるまでは、僕が保証する。」と。毎月私が提示した金額を保証してくれた。
凄い話ですね。
大塚:何年かかるかわかんないけど、世に出ていくまでには少なくとも3年はかかるからねって言われた。けれどそんなに待っていられないから、馬場さんから言われた作品を自分なりにたくさんこなしていった。
馬場さんのオーダー通りの品を作る仕事ですね。
大塚:そう、結果的にはオーダー通りのものを完成させるのに1年かからなかった。3か月ぐらいかな。
3ヶ月!
大塚:それはやはり父とやっていた時からのいろいろな技術が身に付いていたからで、自分でもその技術をもっとアップしたくて先輩のところに行って、その技法を盗む、見てくる、教わっていたから。だから自分でもろくろに対しての技術に自信があった。
馬場さんが言われるものは全て作った。馬場さんの書く図面は最初「こんな感じのどうですか」みたいなラフスケッチで、そのラフスケッチの図面を見てその通りに作っていく。そうすると馬場さんは「あ、こりゃいかん。」って。そうしたら今度、大きさとか寸法とか細かい図面を書いてくる。それを自分が計算し直して作る。作ったときと焼き上がりで寸法が変わるから。
そこまで行くまでは結構色々あった。 私は伝統を守りたいっていう考えだったから。でも、馬場さんは、「それじゃない。新しい益子焼を作っていくんだよ。」って。
反発して「益子焼ってこういうものだ」っていうことを馬場さんに説明する。でも、馬場さんは、「そこはいらない。そこはゼロで考えてくれ。これから生み出すんだから。これまでの伝統っていう部分に関しては、なくていい。ただ僕が言ったことを淡々とやってくれればいい。」と。
でも、そこでもまた私は反発するわけよ。「いやいや、益子ってそうじゃないから」みたいな。でも、馬場さんも「いや、そうじゃない。」その繰り返し。
最終的に馬場さんが言ったのは、「大塚さん、伝統は守るだけじゃないよ。作っていくのも伝統だからね。」
そこで、作る伝統って何だろうって考えた。100年続けば伝統になる、新しいものを作るのも1つの伝統なんだって感じ始めた。
100年続けば伝統になる、新しいものを作るのも1つの伝統になる、深い話ですね。
大塚:馬場さんのところで、言われたものをずっと作るという作業をやって、3ヶ月ぐらいでその行程をある程度までできるようになって。
じゃあ、次は量産ですね。
大塚:そう、でも不安だったのは軽やかな薄い器を作ること。益子焼と真逆だから。
「釉薬は厚みがあるものにかけないと色が出ないから薄いところにはかかりません」と馬場さんに話した。でもそれも全部保証してくれるって言うの。とりあえず失敗するかもしれないけど1個作りましょうって。
馬場さんが「失敗したものも全部僕が買うから。」って言うので、正直“失敗したって知らねえよ”って思いつつ作ってみたらできちゃった。その時に馬場さんから「これですよ、大塚さん」って言われて。
そうか、これが今度新しくなってゆく益子焼なんだなって・・・。
そこから今度は市場に出ていくわけで、たくさん馬場さんから注文が入ってくる。 もう1人じゃ全然やりきれないほど。今まで注文がなかったのに、もう一気にそこで仕事が増えた。
そこである程度の新しい形とかを学んでそれが身についてきて今に繋がっている。
例えば、他ではできませんよって断られた注文の仕事がうちに入ってくる。ある程度、相手が望むものを作っていく。その流れで今いろんな仕事を受けている。
そういった出会いや色々教わってきたことが、今に生きているのですね。
一弘さんにしかできない技術ですよね。
大塚:そうだね、普通の作家さんじゃできないことだね。だから、1人ぐらいそういう作家もいてもいいのかなって思う。
作家としての技術的な高みと、製陶業としての役割が、上手に高いところでマッチしているという感覚。だから、自分をそこに置きたいとか、自分はこういう風に向かっていきたいとかっていうのは、
自然に生まれてくればいいかなっていうだけで。今、本当に目の前に来た仕事を淡々とこなしていって、
そこで面白さとか楽しさとかが見つかれば良いんだよ。数多くやると、この技術を自分の作品に活かそうと、本当に仕事の幅が広がる。よくあるのは失敗すると大体経験値でものを判断して、そこでブレーキをかける。『無理です』って。
でも
自分はそこを超えてやっているから。ある程度は困難な仕事も『チャレンジしてみようかな』って。サンプル作りからやってみていろいろなことを学んでいく。それで最終的に「これだったらできるな」ってなったらそれを見せて、GOサインが向こうから出て、じゃあやりましょうとなる。
焼き物ってその都度いろいろ変化していくから、機械作りでいくつもできる仕事でもないし、自然と関わっている仕事なので、中には失敗するものも出てくるけどね。
そのチャレンジ精神が、今後の益子焼業界にも必要なところですよね。
新しい伝統を
今後、益子焼業界が、どうなっていったらいいと思いますか。
大塚:今はお店側の力がないっていう部分もあると思うんだよね。作家頼みなとこがある。
そうかもしれませんね。
大塚:売れる作家さんの作品だけ集めれば儲かる。だから作家さんたちに頑張ってもらって店はそれを買うということだね。昔は民芸店が「こうにした方がいいんじゃない?こういう注文が入ってきたんだけどできる?」って感じで作家を育ててくれた。
そうすると技術もアップするし経験値も多くなるし、それでお互いにいろんな良いところを共有できた。
これだったらあの作家さんに頼もう、こっちのものだったらこっちの作家さんに頼もうってお店は分かっていた。でも今は売れるものを集めるっていう形。ちゃんとその役割をそれぞれやってもらって、我々はあくまで作る側であり売る側と買う側がうまくマッチングしていけばいいのかなって感じるね。
なるほど。
大塚:でも、作家さんはまた別だからね。作家さんは自分が作りたいものを作って生活していくわけだから、ヒット商品を目指して作っているわけじゃないから。
今、売れるヒット商品を作っている人たちがたくさんいる。でも伝統とかは考えず、売れるものを作っている。実際独立するまでの時間っていうのは短くなっているし、今はいろいろな情報がたくさんあるから、いろいろなところからの知識がいっぱい入ってくるので、あとは技術向きにセンスだけ磨けばいいみたいなね。
本来は基礎となる技術があって、そこにいろんなデザインとか自分の思いとかを載せて作っていく、修行の時代があって、独立して、苦労して売っていくっていう形だった。
今は弟子入りという考え方がなくなっちゃったから、いわゆる雇用に関する制度への対応も考えていかなきゃなんないのかなっていう大変さもある。
確かに弟子入りって聞かなくなりましたよね。
大塚:世の中に出ていくまでには、一度どこかの窯元に入って経験してから出てくという、そういう風になっていけばいいかなって思う。どこの産地もそうだと思うけど後継者不足だから後継者が育つような仕組みにしたいなって思って。例えば、自分の息子たちとか家族は、以前は伝統的な部分で繋がっていっていたけど、今はそういう形じゃないので。入り口は益子に来てもらって、学んでもらって、窯元に入ってもらって、やがてその後を継いでいく人たちができれば良いのかな。家族が全てやるのではなく、外から来た人たちが、益子の良さとか益子の伝統とかを知ってもらって、次の益子焼の伝統を継いでいくっていうような人たちが出てくれば
いいのかなって思う。形はちょっと変わるけど、やり続けるということでは同じことだと思うから。長い目で見て、自分がやっていければな、と思う。


なるほど。
大塚:一応、自分も伝統工芸士だから、技術的な事を伝承していかないといけないっていうのもあるから。自分は伝統という部分と新しい益子焼という部分を両立できればいいかな。
益子は本当にいろいろな焼き物を学んだ人たちが来ているので、新しい人もそういう先輩たちとの繋がりができればもっと仕事の幅も広がるし。
こだわりは必要なのかもしれないけど、こだわる前に取り入れるという柔軟さも必要かな。
隆盛を誇っていた益子焼の時代で、何がすごく重要だったかが明確になったとても良いお話だったなと思いました。
大塚:自分は生え抜きの益子でやってきているから。益子で生まれて益子で育っているわけだから、そういうところは、新しい人よりたくさん感じるところがあるよ。
一方で移住してくる人たちはそれなりにハングリー精神もあるし、自分は父がやってきたレールに乗っちゃったわけだから。
新しく焼き物を学ぶために若い人が来てくれる。こういうパワーを上手に活用して、次の時代に繋げていければもしかすると新しい伝統を作れるかもしれないね。
貴重なお話、本当にありがとうございました。
大塚:ありがとうございました。


- 聴き手:谷島 賢一
益子町商工会 経営指導員